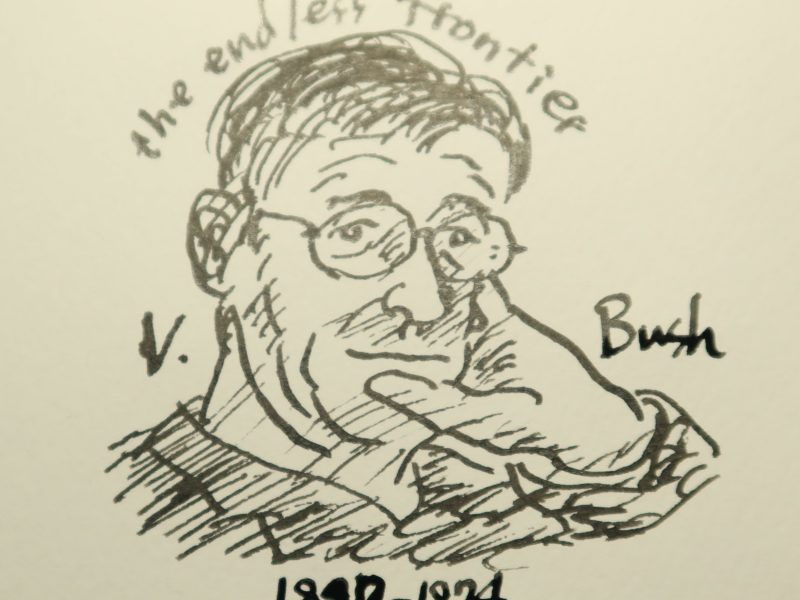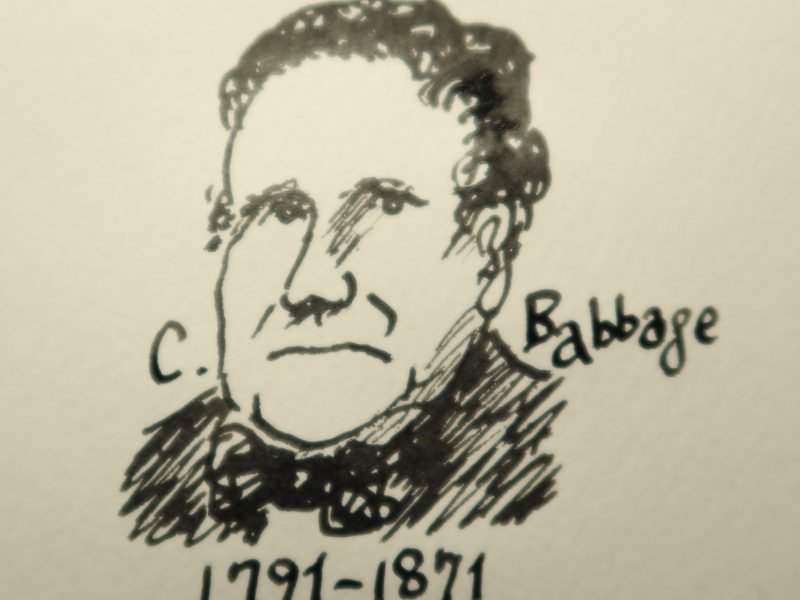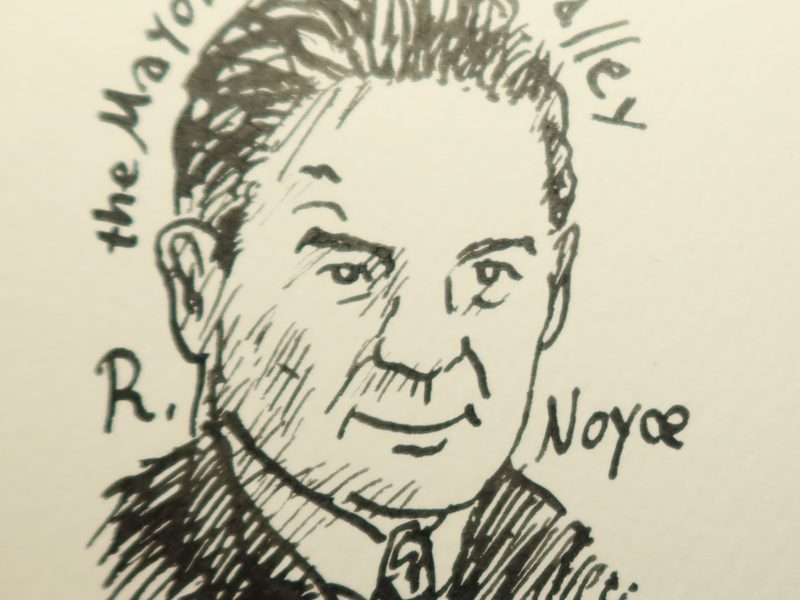計算機の画期は、 1940年代アメリカの「微分解析機まで」と「ENIACから」と見る
- 2021年1月20日
- HirofumiAbe
▼今回は、computer(計算機)の画期、アナログからデジタルに変わる歴史的な時期と「代表者」に着目した。ブッシュさんの微分解析機は、もともとは弾道計算のために作られたものではない。しかし、WWIIが始まって計算パワー …
解析機関から現代コンピュータの祖までのあらましVer.1
- 2021年1月19日
- HirofumiAbe
▼今回は、バベッジさんの解析機関からプログラム内蔵方式のコンピュータEDSACまでの話題をピックアップしてみた。参考にしたのはWikipediaの「コンピュータ」の「歴史」のところ。それとこれまで取り上げてきたコンピュー …
電気通信と計算機&ネットワークの出来事を眺めてみた
- 2021年1月18日
- HirofumiAbe
▼今回の表の狙いは、電気通信と計算機・ネットワークの発展の経緯を並べて頭を整理すること。まず両者の関係は、電気通信が「土台」。計算機・ネットワークは土台の上で我われの経済や暮らしを便利快適にしてくれていることが分かる(そ …
無線通信を調べてみた
- 2021年1月16日
- HirofumiAbe
▼1月15日のブログで整理した通信・コミュニケーションのいろんな方法を対象に、今度は電気の有無と経路の有無で2×2のマトリックスを作ると次のようになる。 ▼電気「なし」の通信はいまや考えられない。ちなみに、のろしは漢字で …
通信・コミュニケーションの方法をリストにしてみた
- 2021年1月15日
- HirofumiAbe
▼コンピュータやスマホでの通信が当たり前になっている今日。これまでどんな方法があったのかを書き出してみた。一緒に通信のとき、目・耳・口のどれを使うのかとか、長所・短所も加えてみた。 ▼するといろいろある。今からやってみた …
アバウト歴史観
- 2021年1月14日
- HirofumiAbe
▼今回は、歴史をアバウトに見てみよう、ってことで。表の「大きな歴史」では、オーソドックスに、特長ごとに時代を5つに区分したもの。 (1)採集生活時代(人類登場から農業や牧畜が広がるまでの期間) (2)農業が始まって定住生 …