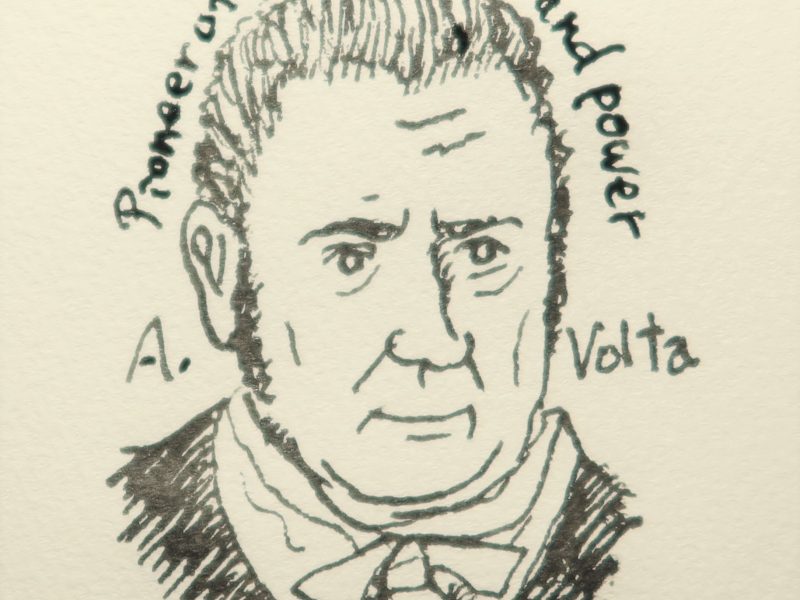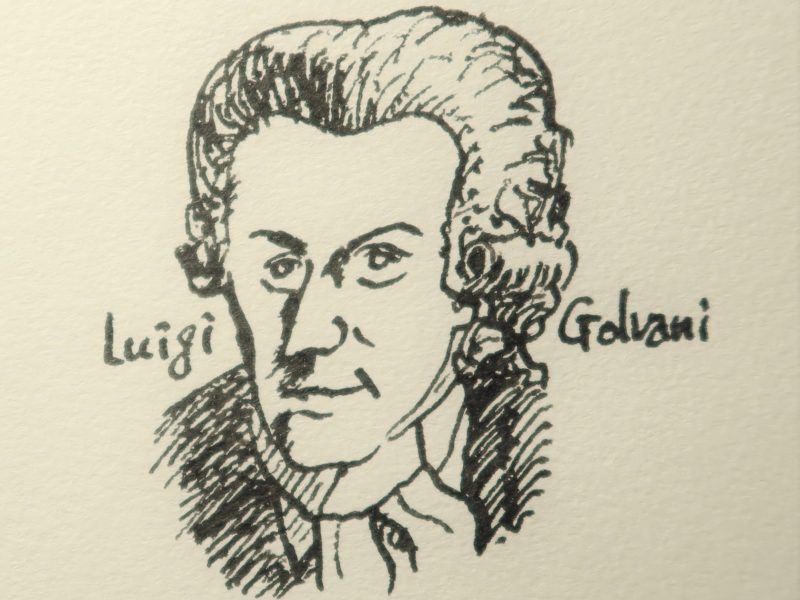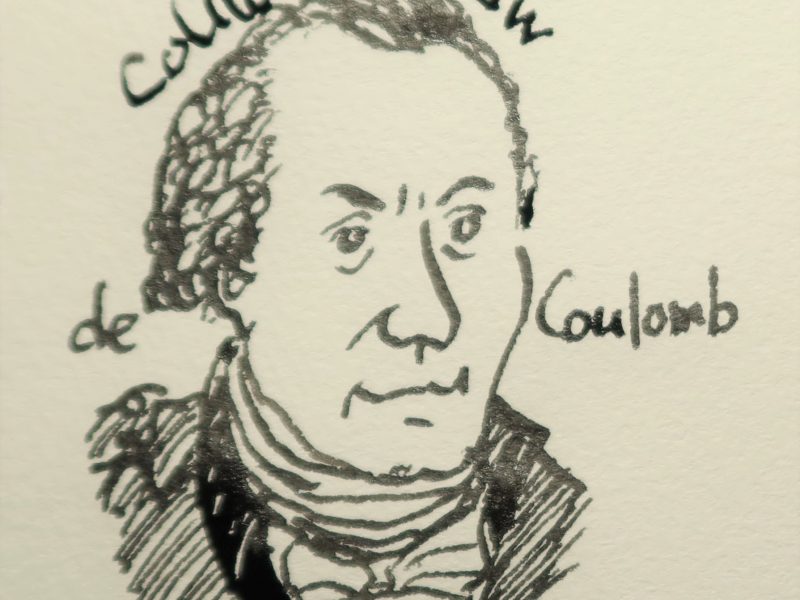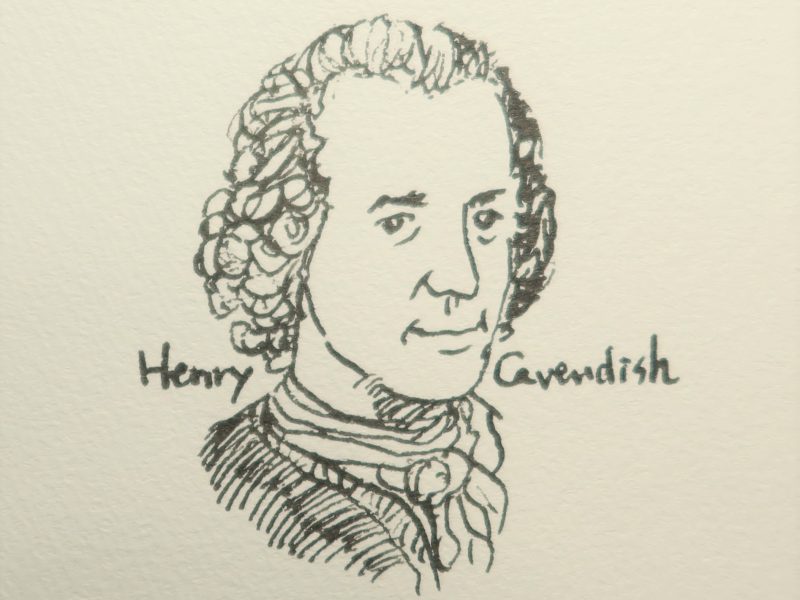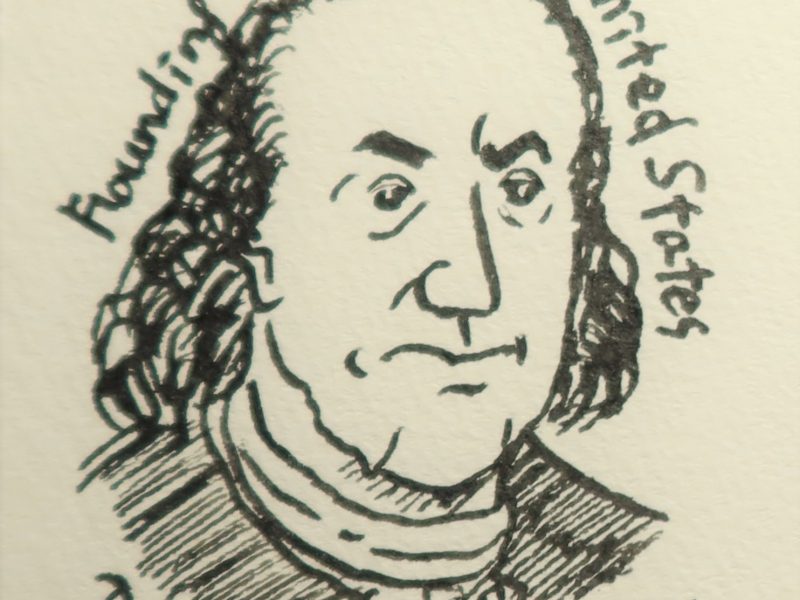Wikipediaの「電気」に出てくる神々(10)ボルタの電池、A・ヴォルタさん
- 2020年12月20日
- HirofumiAbe
▼ガルヴァーニさんがカエルの筋肉から生じた電気を金属棒が拾った、と考えたのに対して、ボルタさんは異なる種類の金属の間に電解液があると電気が生じる、と考えた。それがボルタの電池の始まり。 ▼ボルタの電池の発明で、安定した電 …
Wikipediaの「電気」に出てくる神々(9)生体電気研究の祖、L・ガルヴァーニさん
- 2020年12月19日
- HirofumiAbe
▼解剖したカエルの筋肉に電流を流して動くのを確かめる実験は、一時期の学校教育の理科の定番だった。筋肉の動きと電流に関係があることを確かめる実験の元祖がガルヴァーニさん。専門が解剖だったので、金属器具を使って解剖していたと …
Wikipediaの「電気」に出てくる神々(8)クーロンの法則の、C・クーロンさん
- 2020年12月18日
- HirofumiAbe
▼クーロンの法則で有名(中学理科で出てくる遺伝子の「クローン」ではありません!)電気、磁気の方です。 ▼自分で発明したねじり天秤という装置を使って電荷や磁極の間で生じる引きあう力や反発する力を実験してデータから法則を発見 …
Wikipediaの「電気」に出てくる神々(7)最も大金持ちの科学者、H・キャヴェンディッシュさん
- 2020年12月17日
- HirofumiAbe
▼電気の分野でキャヴェンディッシュさんは実験で次の2つの発見をしている。 1773年(42才)のとき「荷電した粒子間に働く力(反発または引き合う)はそれぞれの電荷の積に比例し、距離の2乗に反比例する」ことを発見。 178 …
Wikipediaの「電気」に出てくる神々(6)アメリカ建国の父にして実験科学者、B・フランクリンさん
- 2020年12月16日
- HirofumiAbe
▼凧を上げて雷から電気を取る実験が有名。しかし、余りにも危険なので、すぐ禁止になった。 めちゃくちゃ運がよくて、ケガもせず、ライデン瓶も割れなくて済んだ。電気にプラス・マイナスがあるなどという発見より、安全が第一だ。 ▼ …
Wikipediaの「電気」に出てくる神々(5)史上初のコンデンサ、ライデン瓶を発明したP・ミュッセンブルークさん
- 2020年12月15日
- HirofumiAbe
▼静電気を起こしても、貯めておく方法なかった時代に蓄電装置(キャパシタとかコンデンサ)であるライデン瓶を発明したのがミュッセンブルークさんチームだ。なぜライデン瓶というかというと、ミュッセンブルークさんがライデン大学の先 …