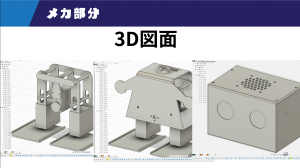当教室の受講生 Kさん(高校2年生)が、対話可能なAIを搭載した「自作スマートロボット」を開発し、その成果を発表してくれました。ハードウェアの設計からAIの連携まで、すべてを自らの手で創り上げた、素晴らしいプロジェクトを紹介します。
きっかけは「余った部品」から
「家にサーボモーターがたくさん余っていたから、何か作ろうと思った」。Kさんのプロジェクトは、そんな日常のふとしたきっかけから始まりました。
しかし、そこから生まれたアイデアは、単なる電子工作の域を超えるもので、自ら歩き、人と対話し、応答する、まさに「スマート」なロボットの開発でした。
設計、電子回路、AI連携など、分野を横断した開発
このロボットの驚くべき点は、その開発領域の広さです。
まず、ロボットの体は3D CADソフト「Fusion360」で1から設計され、3Dプリンターで出力されています。歩行の仕組みといった機械的な構造も、すべてKさん自身が考案したものです。
さらに、内部の電子回路に目を向けると、市販のキットを組み立てるだけではありません。モーターを滑らかに制御するため、オリジナルの制御基板を自ら設計し、発注・製作しています。
そして、このプロジェクトの心臓部といえるのが、AIとの連携です。
自宅サーバーと生成AIを連携させた高度な対話システム
Kさんは、ロボット本体(Raspberry Pi)の処理能力の限界を見抜き、重い処理をすべて自宅の高性能サーバーに任せるという、高度なシステム構成を実現しました。
<対話の仕組み>
1.ロボットがユーザーの声を録音し、サーバーへ送信
2.サーバーが音声認識AI「Whisper」で音声をテキスト化
3.テキストをGoogleの生成AI「Gemini API」に送り、応答文を生成
4.応答文を音声合成エンジン「VOICEVOX」で音声ファイルに変換
5.ロボットが音声ファイルを受け取り、スピーカーから再生する
この一連の流れを、録音開始から最短5秒で実現しています。
担当講師より
Kさんは、入会当初から常に自分のアイデアを形にする強い意志と実行力を持っていました。今回の作品は、機械設計、電子回路、サーバー構築、AI活用という、通常であればそれぞれが専門分野となるような技術を、たった一人で、しかも高校生がまとめ上げたという点で、講師陣の想像を遥かに超えるものです!!
特に、性能のボトルネックを特定し、それを解決するためにクライアント・サーバーモデルという最適な設計を導き出した点に、彼の優れた問題解決能力が表れていますね。今後のさらなる活躍が本当に楽しみです。
無限の可能性へ
Kさんは、「今後は家電と連携させてスマートホーム化したり、言語モデルも自作してみたい」と、すでに次の目標を見据えています。彼が今後どのような素晴らしい作品を生み出していくのか、講師一同、全力でサポートしていきます!